熊本市東区の質屋「質乃蔵(しちのくら)」です。
「質屋って昔はどんな存在だったの?」
「質屋の歴史とは?」
そんな疑問をお持ちの方、きっと多いでしょう。
この記事では、鎌倉時代に始まり現代まで続く質屋の歴史を、現場で聴いた逸話や失敗談を交えながら、ストーリー仕立てで楽しく掘り下げます。
質屋の歴史とは?質屋のルーツと現代まで

質屋の歴史をご紹介します。
驚き!鎌倉時代の質屋
鎌倉時代、宋銭が流通し始めた頃、公家の日記『明月記』に「土倉」という言葉が登場します
実はこれが質屋のルーツ。造り酒屋の蔵が兼業で「お金が足りない人にモノを担保に貸す」最初の形でした。想像してみてください、酒蔵の奥で夜な夜な行われていた、小さな金融の風景を。
庶民の味方になった質屋
江戸時代になると「質屋」という名前に変わり、庶民金融として大活躍。
人口75万人の江戸に2,700軒もの質屋が点在し、280人に1軒という圧倒的な普及率を誇りました。
その背景には、贅沢から節約へと転じた享保の改革(1716〜45年)の影響があり、不景気の中「質屋だけは助かった」という声もあります。まるで、現代の「ATM」のような存在だったのです。
質屋にハプニング?!徳政令で大混乱
戦国時代や室町期、徳政令によって借金が棒引きされ、土倉や質屋が襲撃されたこともありました。
当店でも聞いた実話ですが、「昔は用心棒を雇っていた」という逸話が伝わっています。それほどまでに社会に影響を与える存在だったのですね。まさに金融と社会の関係性を映す鏡です。
明治〜昭和、近代質屋へ
明治時代になると銀行制度が入り、人々の資金調達選択肢は増えました 。しかし、街角の質屋は小口融資の主役として生き残り、1895年に「質屋取締法」が制定されて制度が整備されました。
戦後には全国に2万件を超えるまでに増えましたが、1970年代以降は消費者金融やリサイクルショップの登場により数を減らしました 。
現代の日本の質屋はどう変わった?
1990年代以降、ブランド品が主流になり、買取店舗としての役割が強化されました 。ただし、質預かりや流質品の販売など、金融としての基本姿勢は変わらず、コロナ禍では再び庶民の利便性を支える存在として注目を集めています 。
世界の質屋の起源
古代メソポタミアや中国では紀元前から、衣服や道具を担保にした融資が行われており、最古の金融システムともいわれます。
中世ヨーロッパではロンバルディア地方が発祥とされ、質屋は街中の重要な金融業として定着しました。
現在もヨーロッパ・アメリカをはじめ中国・東南アジアなど、世界各地で庶民の生活を支える金融インフラとして利用されています。
結論
質屋の歴史は、貨幣経済の幕開けから庶民の暮らしを支え、現代のリサイクル・金融の混合モデルまで続く、まさに日本の社会史そのものです。鎌倉・江戸・近代・現代、それぞれの時代で役割を変えながらも、人々の「困った」を支えてきた存在。
今も昔も、質屋は「生活と資金の架け橋」です。
この歴史を知ることで、質屋をただのモノを売る場所ではなく、あなたの暮らしに寄り添う「パートナー」として再発見できるでしょう。

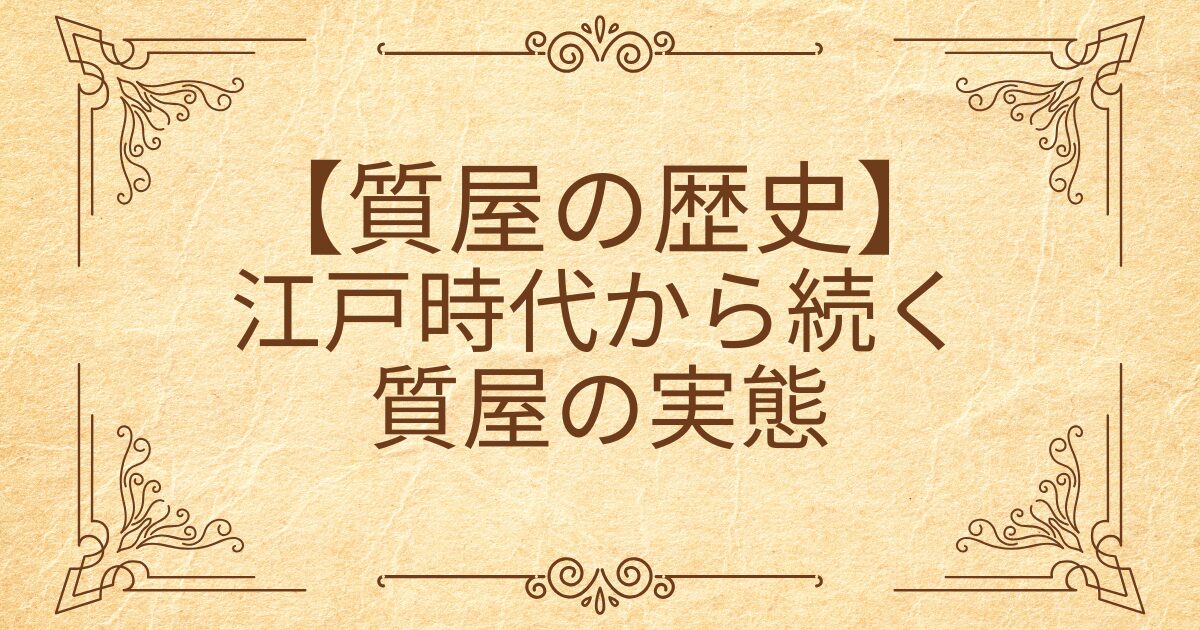





コメント